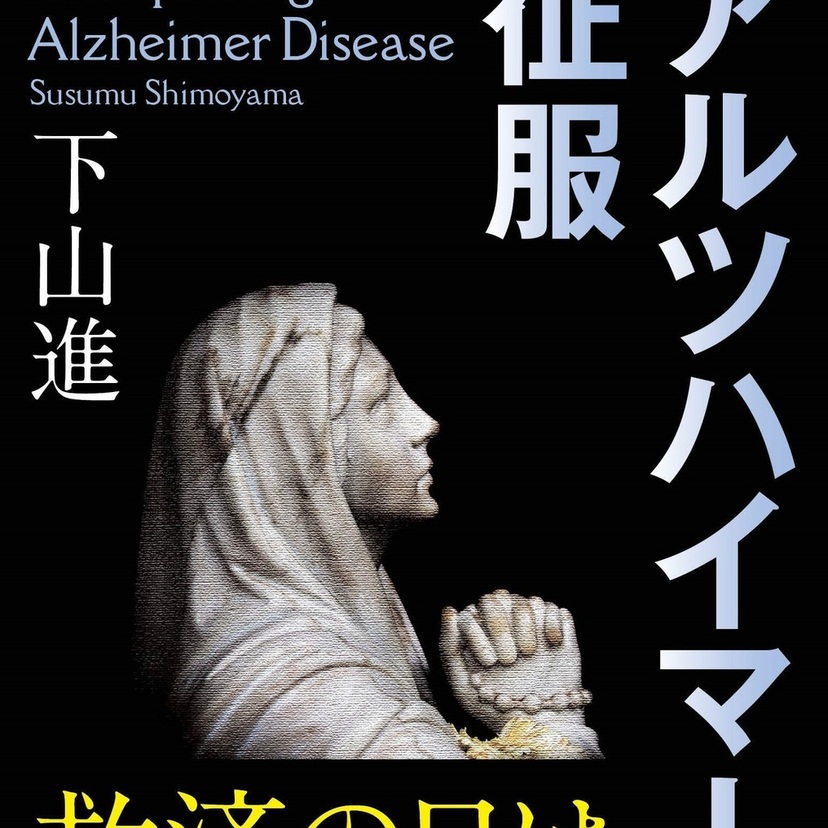――それから18年、よくエネルギーが続いたね。
下山 実は2006年に取材は1回頓挫して、執筆も諦めるんです。
デール・シェンクらが開発したワクチンAN1792は、治験は米国から欧州にまで広げたフェーズ2に進んでいましたが、深刻な副作用が報告されて、結局中止になる。その後に出てきたバピネツマブもうまくいっていない。思った以上に先が長い。
そうすると、遺伝性のアルツハイマー病の家系の人々の運命もようとしてわからない、ということになる。
弘前大学の医学部で、突然変異を追いかけた田崎博一さんに2005年に話を聞きましたが、こんなことを言われました。
「突然変異の場所はわかった。しかし、アルツハイマー病は治療法もなく、将来の展望もない。なので、患者家族に突然変異の有無を伝えることはできなかった」
治療法に対する道筋が見えないかぎりこの本は書けない。そう思い、2006年には一旦このプロジェクトは頓挫する。
――それが再開したのはいつ?
下山 2017年の夏です。前にも話したと思いますが、文藝春秋は当時ごたごたしていて、私も辞めようと思っていた時に、元同僚で直木賞作家の白石一文さんと電話していたら、
「シモちゃん、前にアルツハイマー病の取材していたけど、あれを本にしたらどう?」
と言われたんです。ふと本棚を見たら、30冊近くあった取材ファイルの背表紙は日に焼けていた(笑)。いやー、無理だよなぁと思いながらもファイルを開けて見てみると、これが結構おもしろい。
そこで改めてインターネットで現在の状況を調べてみると、大きな進歩があったことがわかりました。
一番の変化は、2017年にDIAN(優性遺伝アルツハイマー・ネットワーク:The Dominantly Inherited Alzheimer Network)研究が始まっていたこと。アメリカのセントルイスにあるワシントン大学が始めたもので、遺伝性のアルツハイマー病の世界的なネットワークをつくろうというものでした。
前の取材時は、遺伝性アルツハイマー病の人たちはバラバラで孤立していたのをまとめる仕組みができていたのです。日本もそのDIANに参加。これによって、遺伝性のアルツハイマー病の家系の人たちも新薬の治験に入ることができるようになりました。
そして2006年の時点では、遠いように見えていた根本治療薬の開発も、承認申請までいきそうだということを知った。ここで改めて「書けるかもしれない」と思って再取材をし、ついに上梓できた、というわけです。
――ノンフィクションは時間がかかるものだけど、デール・シェンクと会ってから、20年という時間が必要だったんですね。
下山 2002年にデール・シェンクが蒔いた種は「アデュカヌマブ」という薬になって、まさにいま日米欧で承認申請がされ、アメリカではその結果が6月7日には出る予定です。
編集長も三度泣いた
――文章もさることながら、構成がうまい。読んでいて僕は3度泣きました。
まず、プロローグは青森に住むある家族の話から始まる。その一族は40~50代になると、その地の言葉で「まきがくる」、つまり認知症を発症する者が多い。患者の死後に解剖すると脳がどうなっているのかがわかって、そこからアルツハイマー病を解明するドラマに突入していく。
そしてエピローグ近くで、この青森の家族の女性がロンドンで行われた国際会議でスピーチをするんだけど、これが泣ける!
下山 国外に一度も出たことがない遺伝性アルツハイマー病の家系の女性が、ロンドンの総合大学ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンで、世界中の研究者などを目の前にしてスピーチをする。
スピーチでは45歳で発症した母親の人生を語り、母親の結婚式の時の写真をスライドで映しました。
《昔、母はよく「お父さんみたいな人と結婚しなさい」と言っていました。母がなぜそう言っていたか、いまならよくわかります》
スピーチを聞いていた他の国の家族だけではなく、研究者も激しく心を揺さぶられます。
研究者はそれぞれの名誉欲や野心がある。ポストがなければ研究できないし、予算も必要。何より激しい競争のなかで研究をしている。そうすると、時々「自分はなぜこの研究をしているのか」という原点を見失いそうになる。
そんななかで、彼女のスピーチを聞いて、自分が何のために研究を続けているのかを思い出すことができた、そう言っていました。
――もう一つ泣いたのは、ワクチンの開発に参加していた科学者ラエ・リン・バークがアルツハイマー病になってしまう話。まさか、ワクチン開発をしていた科学者自身が発症してしまうとは。夫のレジス・ケリーが健気に看病をずっとしていて、偉いんですよね。
下山 昨年4月にアメリカに2週間行って詰めの取材をする予定だったんですけど、そのうちアメリカでも新型コロナ感染が拡大して、結局Zoomでの取材になって、その時にレジスにも話を聞きました。
ラエ・リンは夜中にしょっちゅう起きるので、その対応をするから寝られない。施設に入れることにしたけど、いい施設は年間12万ドルもかかる。家を売って費用の足しにして、仕事も続ける。自分は施設の近くに住む息子の家の地下室に住んでいて、Zoomで室内を少し見せてもらいましたが、本当に少ししか光が差さない地下室なんですよ。
――ラエ・リンは「Can I help you?」(何か困っていることはない?)が口癖だった。病気が進んでもう会話もままならなくなったのに、施設内で人に会うと必ず、「Can I help you?」」と尋ねる。この話も泣けました。
下山 たとえ病気になってもその人の本質は変わらないんだ、ということがわかるエピソードですよね。

映画『アリスのままで』のモデルにもなったラエ・リン・バーク。