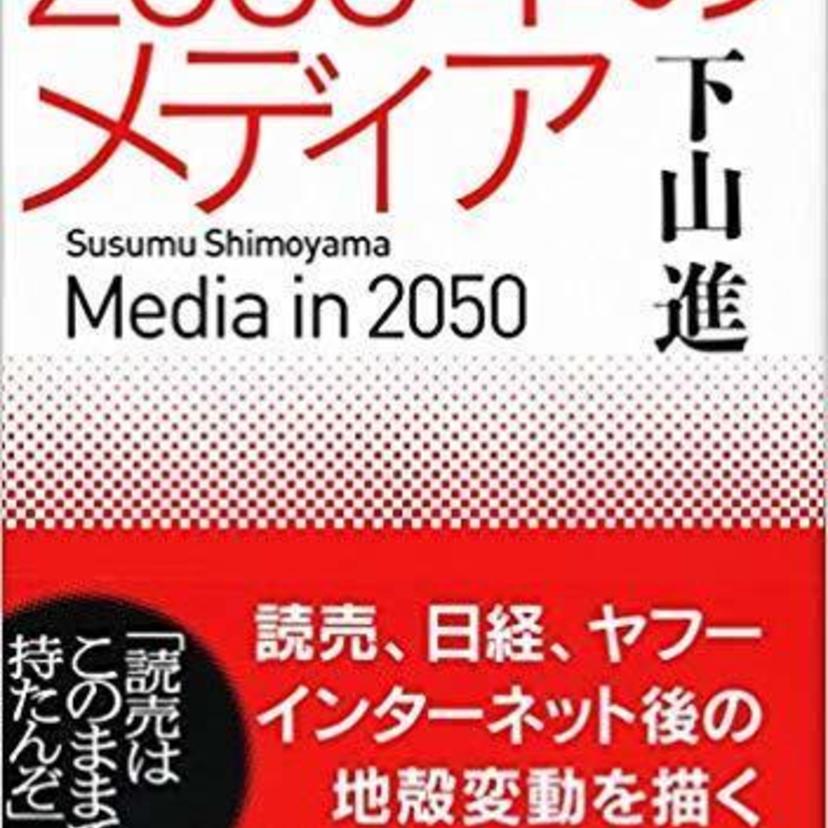ヤフーが読売を狙った理由
──ヤフーは設立当初、共同通信から配信を受けようとした。話は進んで契約までいったのに、いざ配信を始めたその日に、共同通信から「やめてくれ、なかったことにしてくれ」と連絡が来た。
下山 共同通信がブロック紙や地方紙に配信している記事をネットで出してしまえば、新聞が読まれなくなってしまう。共同の加盟紙から猛烈な抗議があったんです。
──次にヤフーが狙ったのは読売新聞。なぜ読売だったのでしょう? たしかに部数は読売が一番ですけど、「新聞界の代表」といえば朝日新聞というのが多くの人の認識だよね。
下山 一番大きな理由は、読売新聞のニュースサイト「ヨミウリ・オンライン」が速報に強かったことなんです。当時、ヤフーは毎日新聞からニュースの提供を受けていましたが、毎日はリアルタイムでニュースを送ってくれるのではなく、紙の新聞が校了した時間にまとめてドサッと来る。さらに、朝刊が配られる時間帯以降でなければ配信してはいけない、といった縛りがあった。それではネットでやる意味がない。
読売は2000年に、編集局と「ヨミウリ・オンライン」を運営するメディア戦略局の間に「ニュース配信センター」という部署を設け、ネットの速報用に記者が記事を書いて、配信センターを通じてメディア戦略局に送っていたんです。
──渡邉恒雄主筆は紙にこだわっているのに、「ヨミウリ・オンライン」をスタートして、しかも速報の体制をとるというのはおもしろい。
下山 渡邉さんは2000年には、ネットなんて歯牙にもかけなかったでしょう。関心もなかった。読売の2001年の紙のABC部数は、1028万部を誇っていましたから。
ヤフーの井上さんは何としても読売を落とさないと駄目だと考え、交渉を進めて2001年8月に契約を結ぶことができた。ここが、ヤフーにとってガリバーに飛躍できる大きなターニングポイントでした。
──ヤフーに対抗すべく、2008年には読売、朝日、日経が共同で「あらたにす」をスタートします。社説、一面トップ、社会面トップなどの比較ができるサイトでした。
下山 企画書にはこう書かれていました。
《ネットの世界において、メガ・ポータルがニュース配信で大きな影響力を持ちつつある現状を打破するため、真のニュース発信者である新聞社が力を合わせ、ネットメディアとしても新聞社の影響力を飛躍的に高めることを目指す》
その意気やよし。が、言い換えると、紙の新聞でやっていることをネットでやろうとしていた。だから新聞案内人たるコラムニストをずらっと並べても、ネットで活躍をしている人は一人もいなかった。
一番の問題は、読売がヤフーから抜けられるかどうか、でした。しかし孫正義さんが当時の社長、内山斉氏のところに駆け込んできて、ヤフーからの離脱をやめるよう頼んだ。
このときの2008年末の契約改定で、ヤフーから読売に払われる情報提供料は倍になります。
社長室長として「あらたにす」の絵を描いたのは、のちにグループ本社の社長になる山口寿一氏ですが、当時は全社的な力を持っているわけではなく、結局、読売はヤフーから抜けられなかった。
──「あらたにす」のPVはイマイチだし、サイトの評判も散々。
下山 そうこうしているうちに、日経が有料電子版をスタートしてしまい、「あらたにす」から日経のサイトに飛んでも記事が読めなくなってしまった。もはやサイトの意味がなくなって、わずか4年強で終了。
3カ月後も通用する記事
──現在、新聞で有料電子版がうまくいっているのは日経だけですが、なぜですか。経済ニュースがネットになじむから?
下山 そういう人は多いのですが、実は大きな誤解です。
日経の記事をよく読むと、経済と言いながらも、それに特化しているわけではありません。たとえば、高齢化社会といいながら、特別養護老人ホームの空きベッドが首都圏の近郊で多くなってきているということを、記者たちが各自治体から集めたデータをもとに実証する記事(2018年12月16日)。
東京・神奈川・千葉・埼玉で、特養待機者が65500人もいるのに、約6000人分のベッドが空いている。なぜなら、介護現場での人材不足によって、受け入れを抑制する施設が増えてしまっているから……。
これは経済の記事ではありません。しかも重要なのは、そうした記事は3カ月後に読んでも古びていないんです。他の新聞が警察や検察、官庁の記者クラブと夜回りでペーパーをとるといういわゆる「前うち」報道に血道をあげている時に、独自の見方による独自の調査の記事を出してきている。
毎日のフロー(流れる)ニュースではなく、フローニュースの持つ意味がわかる、そんな記事を書くようにシフトしてきている。しかも、そうした記事が紙の新聞に載る前日の午後六時には、電子版に「イブニング・スクープ」として出してしまう。
こうしたやりかたで、現在、日経電子版の契約者数は72万人です。有料電子版は2010年3月から始まっていますが、ちょうどその間の紙の部数の落ち込みをカバーして、日経は売上がリーマンショック以降も落ちていない日本でただ一つの新聞社です。
1970年代に社長だった圓城寺次郎が「経済に関する総合情報機関」を提唱し、日経をつくりかえます。紙はもっている情報を伝える手段のひとつにすぎない。アーカイブは日経テレコン、速報は日経クイック、企業分析は日経NEEDSという具合に、新しい情報の出口を設けました。
圓城寺さんは当時、「いつか新聞も出していた会社と言われたい」と言っていましたが、20~30代だった社員はその考えを肌身で感じていた。彼らが40~50代になった2000年代半ばに、杉田亮毅さんは日経電子版を決断します。しかし、それが実際にできたのは、圓城寺次郎以来のDNAが共有されていたからです。