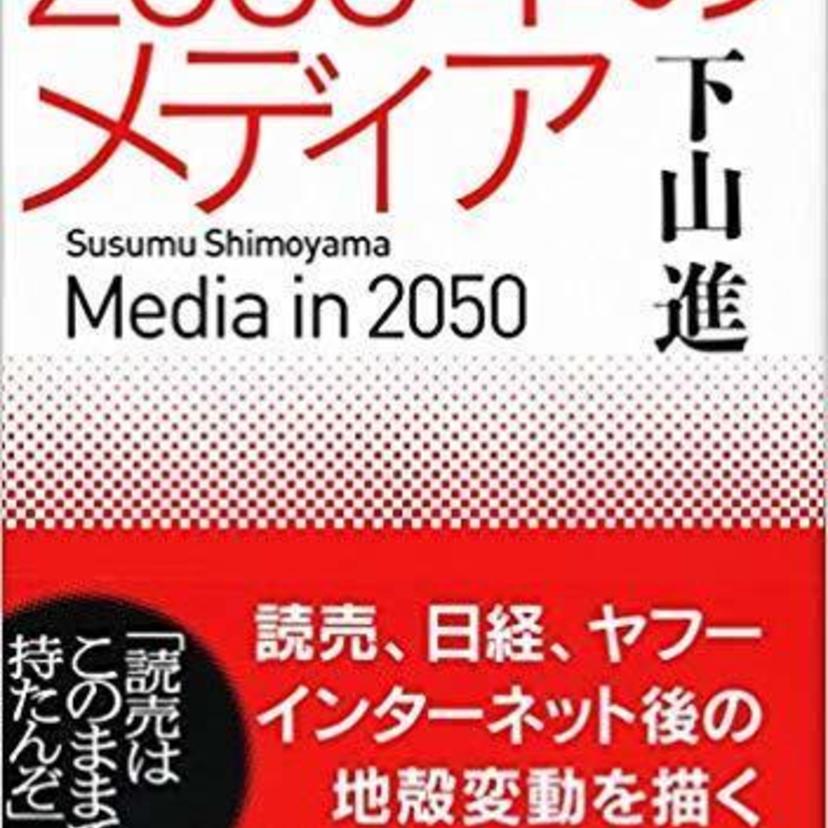日本のヤフーだけが成功
──ヤフーはそもそもアメリカの会社で、96年にソフトバンクと合併して日本のヤフー株式会社が設立され、国内初のポータルサイト「Yahoo! JAPAN」が誕生した。ところが、アメリカのヤフーは失敗に終わり、日本のヤフーだけは成功した。
下山 アメリカのヤフーの失敗は、日本のヤフーの成功の裏返しです。
ヤフー・ジャパンの初代社長の井上雅博という人は、非常にすぐれた経営者でした。東京理科大学の数学科の出身でエンジニアです。プラットフォーマーとして成功するには、自分たちがコンテンツを作ってはだめだということをよくわかっていた。
ここが他の企業がよく間違えるポイントで、たとえばライブドアでも楽天でも、2000年代前半にTBSやフジテレビの株を取得しようとし、垂直統合すれば成長できると考えた。しかし、いずれも失敗します。
井上さんはそうではなく、TBSもフジテレビも日テレも、等しく付き合っていくことで、プラットフォーマーはメディアのコンテンツをフルに活用できる、と考えたのです。
アメリカのヤフーもここを間違えた。メディアになろうとして記者を雇い、記事を書かせ、動画コンテンツのプロデューサーも雇った。つまり、自前でコンテンツを作って発信をしようとした。その結果、検索のアルゴリズムに特化したグーグルとの競争に負けてしまう。
実は、自分たちでコンテンツをつくるという話は、ヤフー・ジャパンでも出ていたんです。読売新聞出身の奥村倫弘さんが、自分たちで取材をし、記事を書いて、ニュースを出してはどうかと提案した。ところが、井上さんはそれを拒否。
「そんなことをやって、それで読売が(記事配信から)抜けたら、責任が取れるのか?」
ヤフー・ジャパンが独自で取材をし、記事を書き始めれば、それまで記事を提供してくれている媒体企業と競合関係になる。そうなれば、先ほど言ったとおり、どことも等分で付き合うことで成り立っていたプラットフォームとしての地位が揺らいでしまう。
どこで誰が見ても同じ8本
──ヤフー・ジャパンの一番の武器は「ヤフー・トピックス」(通称・ヤフトピ)。
下山 これもまた日本独自のものです。トップページの真ん中に8本掲載してあるトピックスで、スタートからいまでもそうですが、いつ誰がどこで何で見ようが、同時刻にはこの8本は同じものが表示されるんです。たとえば、グノシーやスマートニュースなど他のニュースサイト(アプリ)では、AIがアクセスしてくる人のログをみて、その人の趣味や嗜好に合わせたニュースを表示する。
しかし、ヤフトピは誰がアクセスしようと、8本は同じ8本が表示されるようになっている。しかも上の4本は、政治、経済、国際などの硬派のニュースが必ず並び、芸能やエンタメは下の4本で表示されます。これらの8本のニュースは、毎日媒体各社から送られてくる5000本の記事のなかから、ヤフトピの編集部が人力で選んでいるんです。AIは使っていない。
しかしだからこそ、本当に大事なニュースを伝えるという公共性をずっと大事にしてきている。
──誰が考えついたんですか?
下山 奥村倫弘さんです。いま何が重要なニュースなのかを提示する。クオリティ(質)がプロフィッタビリティ(収益性)に結びつくのだと、よく理解していた。
AIが選ぶやりかたは、どうしてもその人の見たいニュースしかみせないフィルターバブルになります。それは短期的にはPVを稼げるかもしれないが、長期の持続性はない。現在のヤフーの成功は、そのことをよく物語っています。
──ヤフトピに掲載するニュースは、誰がどう選んでいるんですか?
下山 編集部に200人くらいいて、5000本のなかから彼らが選別して、見出しを付けて掲載しています。ヤフトピに載らなかったものは、別途、各ジャンルのニュースの欄に掲載されていく。ですから、ヤフーには記者はいない。編集部には編集者とエンジニア、そしてデザイナーがいるだけです。
──新聞社や出版社の人間が、ずいぶん移籍していますよね。
下山 編集部のほとんどは旧メディアから来た人ばかりで、ようやく最近、ヤフー生え抜きの人が出てきた感じですね。

1998年に「ヤフトピ」が登場。最初は右側に配置されていた。