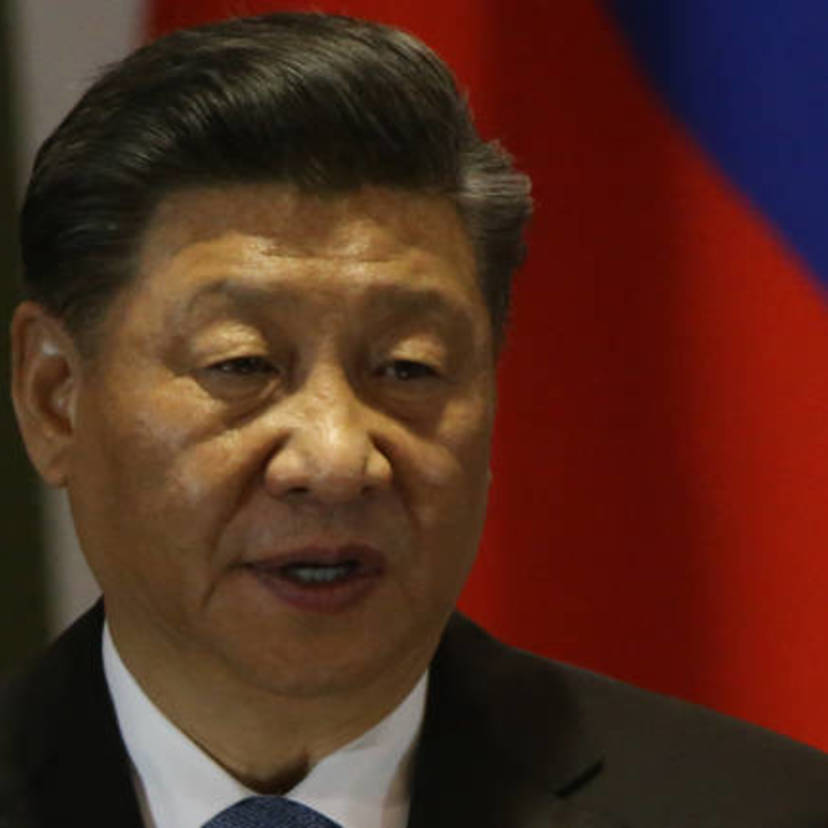出版自粛が自由を葬る
ポンペオ演説をファクトで実証する『目に見えぬ侵略』がいかに衝撃的であったかは、出版に至るまでの経緯を知れば察しがつくかもしれない。著者のハミルトン氏は、懇意の出版社と契約を取り付けていたのに、草稿を送る段階になって出版を断ってきたからだ。出版社が北京からの報復や、オーストラリア国内で中国の手先となって行動する人々を恐れたのだ。
対中配慮は自由の自殺である。この一件をもってしても、オーストラリア社会がいかに中国から無言の圧力にさらされてきたかが分かる。これが戦前の軍国日本で起きた出版拒否ではなく、現代のしかもイギリス連邦の一国で起きた事実に愕然とするのだ。
1936年(昭和11年)に陸軍青年将校が決起した「2.26事件」で、東京帝国大学教授の河合栄治郎が「二・二六事件の批判」を書き上げた際の事情がそうだった。声をかけた新聞社や出版社が、この時ばかりは掲載に尻込みをした。しかたなく、河合は「帝国大学新聞」に掲載するしかなかった。
著書が発禁処分を受け、帝大を追われた河合と違い、幸いにもハミルトン氏の翻訳本はこうして手にできる。これら日豪二つのケースを考えると、「自由の確保は私たちの時代の使命だ」と述べたポンペオ国務長官の発言が、ズンと現実味を帯びてくるのである。
この『目に見えぬ侵略』は、米ソ冷戦を描いたドキュメンタリー映画のように、北京の秘密会議から始まる。それは2004年8月半ば、世界に散らばる中国の外交官が北京に集められた場面だ。当時、この国の最高権力を握る中国共産党総書記、胡錦濤は、何事かといぶかる外交官たちの前で、党中央委員会がオーストラリアを「中国の周辺地域」に組み込むべきであると決定したと述べた。
属国化戦略は日本にも
「周辺地域」とは従来、陸の国境を接する国々を指しており、中国共産党にとっては力ずくによって併合するか、あるいは中立化すべきターゲットになる。南シナ海の大半を独り占めすることになると、南半球にある遠方のオーストラリアでさえグンと近くなる。
しかも、中国の経済成長に必要な資源の供給国であり、かつ米豪同盟にクサビを打ち込む意味からも欠かせないとの勝手な理屈だ。
ハミルトン氏が聞いた情報提供者は、その場にいた人々に「経済、政治、文化など、あらゆる面でのオーストラリアに対する包括的な影響力」を獲得せよという密命が与えられたという。本書の副題にある中国のオーストラリア支配計画の始まりである。
北京はオーストラリアの政治と経済を牛耳ることにより、アメリカに「ノーと言える第二のフランス」を西太平洋に構築する野望を描いた。
あのポンペオ国務長官の演説では、アメリカ国内でも中国共産党がこれまでの善意に満ちた対中「関与政策」を利用して、研究所、高校、大学、さらにPTAにまで「宣伝活動家を送り込んできた」と表現している。
レイFBI長官の演説もまた、中国の情報機関の要員だけでなく、アメリカに派遣される民間企業の社員、メディア、研究者、大学院生など幅広い人材を活用しているという。
実際にオーストラリアでは、中国大使館によって創設された親中団体に先導されたビジネスマン、大学の関係者、それにオーストラリア内に100万人以上いる中国系住民に影響を拡大していた。
これがオーストラリアを赤く染める「属国化戦略」である。中国共産党の狙いの一つが、米豪同盟の解体にある以上、海を隔てて向かい合う日本に対しても、日米同盟の分断を狙って「浸透戦術」が発動されているはずだ。昨日のオーストラリアは今日の日本なのだ。