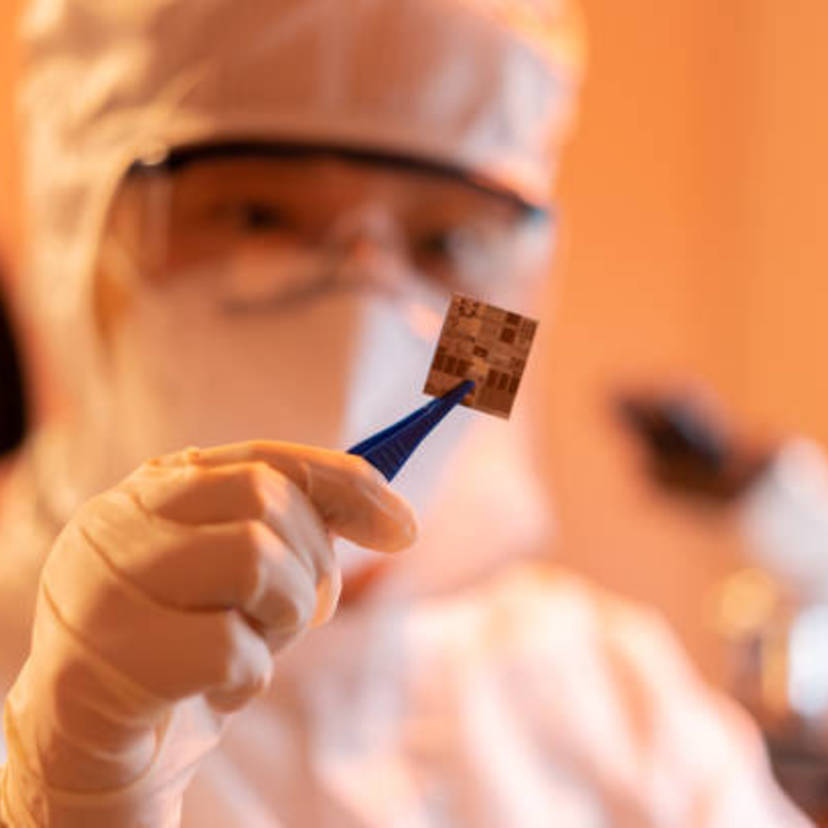30年前にもあった「チップウォー」
実は、本書の原題である「チップウォー(Chip War)」と全く同じタイトルの書籍が、30年前の1991年に刊行されている。フレッド・ウォーショフスキー著、青木榮一訳『チップウォー』(経済界)だ。邦訳版の副題は〈技術巨人の覇権をかけて〉〈日米半導体素子戦争〉。
日本が半導体産業でアメリカを制するに至った強みを紹介しつつも、日本の市場論理を「理解できない」と批判し、のちに台頭してくる国として台湾と韓国を挙げている。
「スパコンにまで日本製ICチップが使われている!」「CIAが憂慮」などの文字を見ると、やはり「ライバル」が日本から中国に入れ替わっただけに見える(当時の日本が「生産性が高い」、その理由は「夏休みの山盛りの宿題に苦労するほどの教育制度が奏功しているからだ」と解説されているのには笑ってしまったが)。
こうしたアメリカの認識を「一位のアメリカは常に二位の国を叩く」と言えばわかりやすいのだが、そのための戦略は常に奏功するとは限らない。
本書の後半は半導体を巡る米中の戦いを描き、それが比喩ではなく実際の「中台戦争(台湾有事)勃発」に至る可能性や、今や半導体生産の世界的シェアを誇る台湾の生産能力の低下が、世界的不況を引き起こしかねないことを指摘している。
当然、中国は現状を単なる経済戦争、半導体戦争とは位置付けていない。「ここで競り負ければ国家の存続そのものに影が差す」ことを重々承知している。
本書が引く中国政府のアナリストによる「(米中の緊張が高まれば)われわれはTSMCを奪取するしかない」との発言を、どう見るべきか。課題は多いだろう。
日の丸半導体復活か、二度目の敗戦か
さて、翻って日本はどうか。
日本の「半導体産業の衰退」の原因は、1986年の日米半導体戦争で不利な条件を押し付けられたことが主因、とする解説が多い。だが、もちろんそれだけではない。著者のミラーは日本が不況に陥り、半導体産業への潤沢な投資が行われなくなったからだ、と指摘する。
事実、産業の躍進期には低金利で膨大な投資だけでなく、政府の補助金も半導体産業に注ぎ込まれていた。こうした投資や補助金の重要性を、戦略家、エドワード・ルトワックは「戦場に投入される火力」に例えたが、そうしたバックアップがなくなれば、戦況の悪化、業界の衰退は当然に見える。
しかしより根源的な問題として、やはり諸外国のように、半導体が軍事と密接にかかわる戦略物資であり、さらには自国の存立を支える基幹産業であるとの視点がなかったことが敗因のようにも思う。なにせ、日本政府が半導体を「戦略物資」と位置づけたのは、実に2022年の経済安全保障関連法案の議論が起きてからなのだ。
ただし、日本でも30年以上前に、「半導体は戦略物資である」ことを認識していた人もいる。森田昭夫と『「NO」と言える日本』(光文社)を出した、石原慎太郎氏だ。
本書で引用されている、当時の石原氏の主張を読むと「半導体の本質を当時、ここまで理解していた人がいたのか」と驚く。
とはいえ、同時に「いくら投資力がなくなったとはいえ、そのことに言及した書籍が100万部以上も売れたのに、日本の半導体産業が顧みられなかったのはなぜか」、という新たな疑問も生じるのだが。
現在、日本政府は民間企業とともに「日の丸半導体復活、最後のチャンス」とばかり大きく旗を振っている。果たして30年後に書かれる「半導体戦争史」で、日本は主要プレイヤーになっているだろうか。とにもかくにも、「二度目の敗戦」だけは免れたいところだ。

ライター・編集者。1980年埼玉県生まれ。月刊『WiLL』、月刊『Hanada』編集部を経てフリー。雑誌、ウェブでインタビュー記事などの取材・執筆のほか、書籍の編集・構成などを手掛ける。