──なぜ業平は、これほど長く日本人に愛され続けたのでしょうか。
高樹 一つはやはり色香。日本人は色の世界、男と女の話が好きなんでしょうね。しかも権力闘争からは距離を置いた男が、歌や心遣いの細やかさで多くの女性と関係していくというのがいい。権力者が色恋を語っても、それは力でどうにでもできてしまったり、打算めいたものが渦巻いてしまいますが、業平のような権力から離れた恋については「これこそ純粋なものだ」と人々に感じさせたこともあるのでしょう。
むしろ業平の場合は、女性のほうが並々ならぬ立場に就くことになって、一夜限りの恋になってしまったりもする。権力から外れた男のままならぬ恋だからこそみんな興味を持ったし、応援もしたんじゃないでしょうか。
もう一つは、冒頭でも触れた「貴種流離」の美です。海外にも、高貴な生まれの人が苦労の末、成長して為政者になるという話はあります。しかし業平は、権力の主流に乗らず、だからこそ風流人であるというふうにも思われています。
これは日本の美の感覚と通じるものがあって、私たちが思っている日本の美──「もののあはれ」や「わびさび」というようなもの──の原型を作ったのは業平が最初だったんじゃないか、とさえ思います。
──「世の中に絶えて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし」という業平の有名な句は、一千年後の私たちでも、思わずそのとおりと思ってしまいます。
高樹 実は、この当時の桜はいまの「ソメイヨシノ」とは違うので、ハラハラと散るわけではないのですが、それでも桜が咲いた、散ったと気がかりなのは、いまの私たちも同じですよね。
──桜と自分とを重ね合わせるのも日本人的な感覚です。高齢になると「来年の桜は見られるかしら」と。
高樹 人は必ず衰える、そして死を迎える。そのことをどう受け入れるか。業平は若い頃の女性たちとの巡り合いを残すとともに、それだけではない死へ向かう自らの旅路までも歌に残しました。衰え、ついに消えゆくその姿にさえ、美と悲しみが同居しうるのだ、という日本の美的感覚を最初に言葉として表したのは業平だった──。
もしそうだとすれば、日本人の意識にとてつもなく大きな価値観をもたらしたことになりますね。
(初出:『Hanada』2020年7月号、インタビューアー:梶原麻衣子)
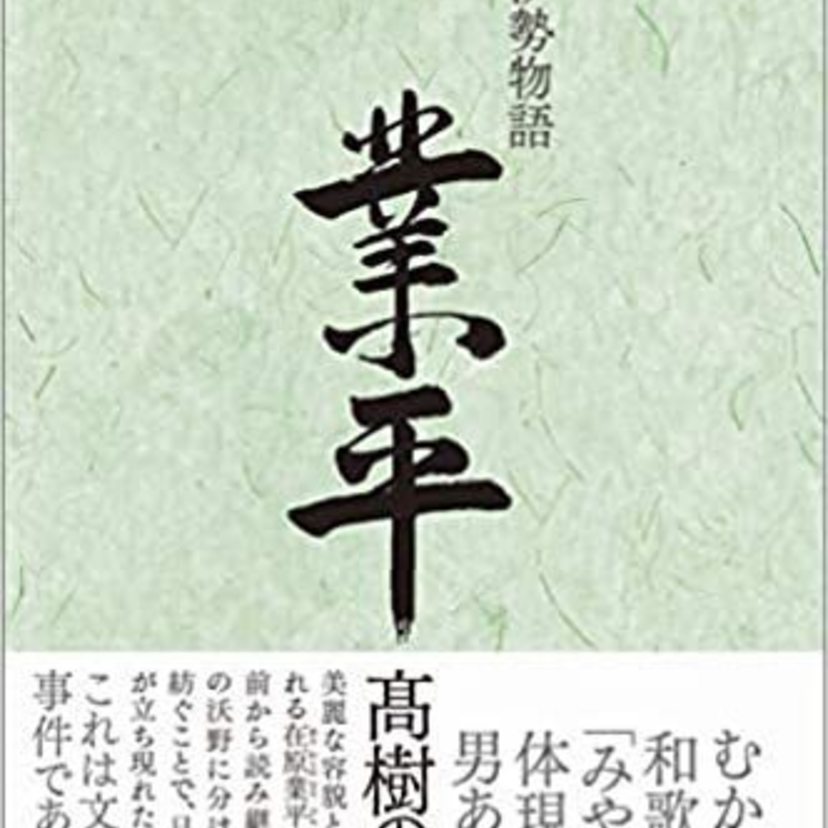
著者インタビュー|高樹のぶ子『小説伊勢物語 業平』
千年読み継がれてきた歌物語の沃野に分け入り、美麗な容貌と色好みで知られる在原業平の生涯を日本で初めて小説化。「古典との関わり方として、私は現代語訳ではなく小説化で人物を蘇らせたいと思ってきました」(「あとがき」より)という著者に業平の魅力などを語っていただきました!
関連する投稿
【読書亡羊】「右派市民」って誰のこと? 松谷満『「右派市民」と日本政治』(朝日新書)|梶原麻衣子
その昔、読書にかまけて羊を逃がしたものがいるという。転じて「読書亡羊」は「重要なことを忘れて、他のことに夢中になること」を指す四字熟語になった。だが時に仕事を放り出してでも、読むべき本がある。元月刊『Hanada』編集部員のライター・梶原がお送りする時事書評!
【読書亡羊】「道産子アメリカ人」が静かに鳴らす警鐘が聞こえるか ジョシュア・W・ウォーカー『同盟の転機』(日本経済新聞出版)|梶原麻衣子
その昔、読書にかまけて羊を逃がしたものがいるという。転じて「読書亡羊」は「重要なことを忘れて、他のことに夢中になること」を指す四字熟語になった。だが時に仕事を放り出してでも、読むべき本がある。元月刊『Hanada』編集部員のライター・梶原がお送りする時事書評!
【読書亡羊】ベネズエラ国民「私たちを見捨てないで!」 トランプがマドゥロ拘束に動くまで 外山尚之『ポピュリズム大国 南米』(日本経済新聞出版)|梶原麻衣子
その昔、読書にかまけて羊を逃がしたものがいるという。転じて「読書亡羊」は「重要なことを忘れて、他のことに夢中になること」を指す四字熟語になった。だが時に仕事を放り出してでも、読むべき本がある。元月刊『Hanada』編集部員のライター・梶原がお送りする時事書評!
【読書亡羊】「麻辣強国」VS「マサラ強国」…米中印G3時代への準備はいいか 中川コージ『インドビジネスの表と裏』(ウェッジ)|梶原麻衣子
その昔、読書にかまけて羊を逃がしたものがいるという。転じて「読書亡羊」は「重要なことを忘れて、他のことに夢中になること」を指す四字熟語になった。だが時に仕事を放り出してでも、読むべき本がある。元月刊『Hanada』編集部員のライター・梶原がお送りする時事書評!
【読書亡羊】熊はこうして住宅地にやってくる! 佐々木洋『新・都市動物たちの事件簿』(時事通信社)|梶原麻衣子
その昔、読書にかまけて羊を逃がしたものがいるという。転じて「読書亡羊」は「重要なことを忘れて、他のことに夢中になること」を指す四字熟語になった。だが時に仕事を放り出してでも、読むべき本がある。元月刊『Hanada』編集部員のライター・梶原がお送りする時事書評!
最新の投稿
被害者続出でも国は推進 成年後見制度 悲劇を生む構図|長谷川学【2026年3月号】
月刊Hanada2026年3月号に掲載の『被害者続出でも国は推進 成年後見制度 悲劇を生む構図|長谷川学【2026年3月号】』の内容をAIを使って要約・紹介。
【読書亡羊】「右派市民」って誰のこと? 松谷満『「右派市民」と日本政治』(朝日新書)|梶原麻衣子
その昔、読書にかまけて羊を逃がしたものがいるという。転じて「読書亡羊」は「重要なことを忘れて、他のことに夢中になること」を指す四字熟語になった。だが時に仕事を放り出してでも、読むべき本がある。元月刊『Hanada』編集部員のライター・梶原がお送りする時事書評!
山上銃と黒色火薬 本当に単独犯行なのか|照井資規【2026年3月号】
月刊Hanada2026年3月号に掲載の『山上銃と黒色火薬 本当に単独犯行なのか|照井資規【2026年3月号】』の内容をAIを使って要約・紹介。
『Hanada』プラス連載「今週もおかしな報道ばかりをしている『サンデーモーニング』を藤原かずえさんがデータとロジックで滅多斬り」、略して【今週のサンモニ】。
【安倍元総理暗殺事件 裁判傍聴記③】山上徹也、無言の退廷|楊井人文【2026年3月号】
月刊Hanada2026年3月号に掲載の『【安倍元総理暗殺事件 裁判傍聴記③】山上徹也、無言の退廷|楊井人文【2026年3月号】』の内容をAIを使って要約・紹介。


