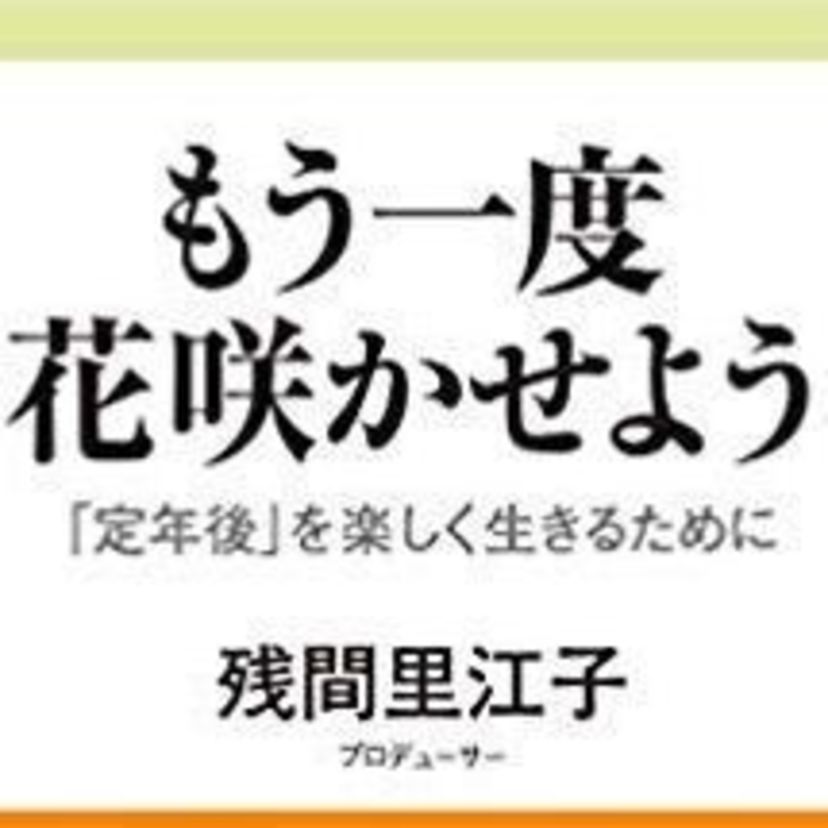『もう一度 花咲かせよう 「定年後」を楽しく生きるために』残間里江子 著

残間里江子(ざんま りえこ)
1950年仙台市生まれ。アナウンサー、雑誌記者、編集者を経て、1980年、株式会社キャンディッド・コミュニケーションズを設立。雑誌「Free」(平凡社刊)編集長、山口百恵著「蒼い時」の出版プロデュース、自主企画事業、映像、文化イベント等を多数企画・開催。
撮影 佐藤英明
年齢を過剰に意識
――「人生100年時代」といわれています。まえがきには〈会社をリタイアしても、人生は終わっていない。本書は人生に最後の花を咲かせたいと思っている全ての大人たちに捧げる応援の書である〉とありますね。団塊(だんかい)の世代の一員である残間さんが、同世代の人たちとの交流や仕事を通して感じたことや、日常のこと、家族について考えたことなどを綴っていらっしゃいます。
残間 びっくりしたのは、知人がメールをくれて、「最後まで読んでも、どうやったら花を咲かせられるのかの方法がまったく書いてありませんでしたね」といわれたこと(笑)。これはすごく褒めてくれたのよ。逆にいえば、「そんなハウツーを本に期待しているようじゃダメだよ」ということでしょう。
実はこれを書いている間、わたし自身が心身ともに絶不調だったの。3年半前に15年以上介護した母が亡くなったとたん、わたしにもいろんな病気が出てしまって、いちばんひどいときには9つの診療科に通っていた。棘突起(きょくとっき)過敏症とかブシャール結節とか、死に直結するものではないんだけど……。
気持ちも疲弊してしまって、なんかもう人生全部ダメだって思って落ち込んでいました。わたしは来年、古稀(70歳)なんだけど、これまでは年齢なんて意識したことがなかった。それなのに過剰に意識するようになり、「歳をとるってこんなに可能性がなくなるように感じるものなのか、こんなにめげることなのか」って。
だから、「もう一度花なんか咲くわけないよ」なんてグズグズいいながら書いてたのよ。
――子どもの頃から「病気の問屋」といわれるくらい、たくさんの病気を抱えていたそうですが、一見とても元気そうに……。
残間 丸顔だからね(笑)。コロコロ街を転がって歩いてるみたいに思われてるから、病気だの落ち込んでるだのといっても説得力がない。
まあ、しおれた顔をしてても似合わないから外では笑ってて、でも家に帰ってくると溜め息をついて、将来も未来もないなあって。
それが2年くらい続いたのかな。だけど、それでもとにかく生きてる。周りを見ると、ガンになってる友だちもけっこう多いんですよ。わたしだって、いつどうなるかわからないじゃない。このまま萎えたんじゃあなーって、萎えてるのも少し飽きてきたわけ。ずっとグズグズいってたんだけど、でもこのグズグズがあったからこそ、この本が書けたともいえるんだけどね。
若い頃は、手にしたものをいったん全部捨ててゼロになったところからこそ新しい花を咲かせるエネルギーが出てくるのだと思っていたけど、ちょっと待てよ、今はもう、そうもできないかもしれない。だったらいまあるご縁みたいなものや、わたしごときにも声をかけてくれるひとを大切にしなくちゃいけないんじゃないか。
相手から「もう必要ない」といわれるのが怖いから、自分から去っていくということも昔ならできたけれども、今はむしろ、必要とされている間はちゃんとそれに向き合うべきなんじゃないかと思うようになってきた。雑誌やラジオ、イベントなどの仕事にしても。
豪華なランの花なんかは好きじゃないけど、せっかく生まれてきたんだから、そうやって野辺に咲く小さな白い花くらいは、やっぱりもう一度咲かせたいわよね。