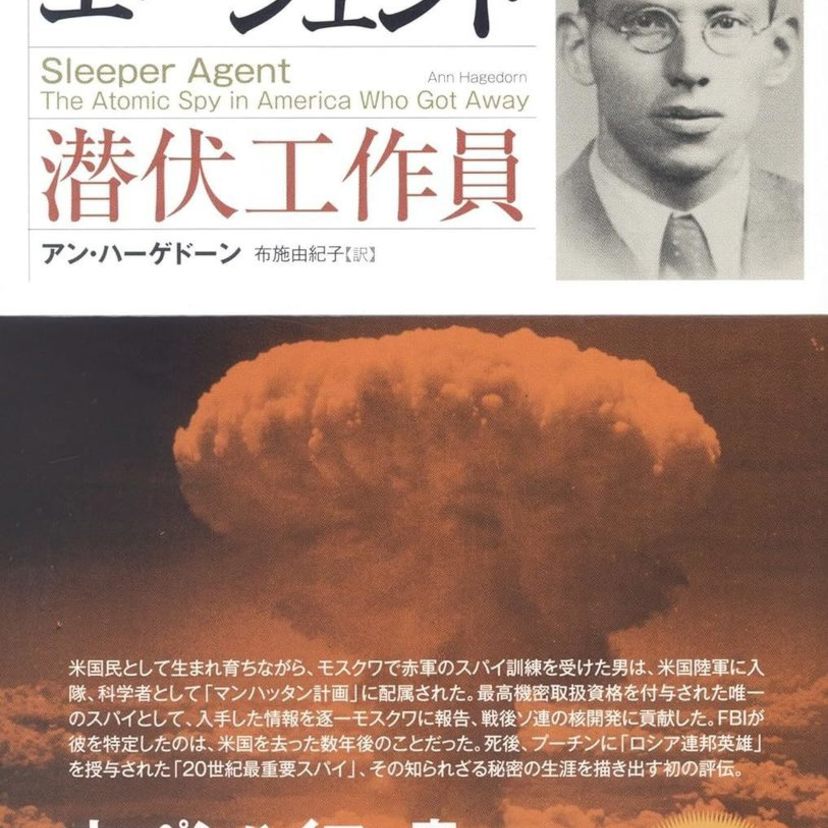国を持たないユダヤ人の悲哀
アメリカでのコヴァルの活躍は本書を読んでいただくとして、実に今日的なのはユダヤ人であるコヴァルがアメリカとソ連という対立する大国の両方で、人種を理由に差別的風潮に直面することである。
国を持たないユダヤ人だからこそ、国を超えて各国に居住している。差別を受けるからこそ、移住せざるを得ず、だからこそ国家に対する忠誠を示す必要に迫られる。だがそれがスパイとして格好の素質・下地となり、故に「ユダヤ人は実際のところ、誰の味方なのかわからない」という偏見を強めもするのだろう。
本書が描き出すコヴァルの人生を、「アメリカ人でもソ連人でもない、一人のユダヤ人」として見ると、また違った読み方ができるのだ。
原爆によって終わった第二次大戦が終戦してまもない1948年に、ユダヤ人の国家であるイスラエルが建国された。各地で差別やジェノサイドの憂き目にあってきたユダヤ人が「自分たちの国」を持てたことはどんなにか誇らしい出来事だったろうと思う。
そう考えると、ナショナリズムの高揚や他国をしのぐ情報機関の存在などからも感じるように、イスラエルは今まさに19世紀から20世紀の国民国家の足跡をなぞり直しているのかもしれない。
だが、だからと言って今のイスラエルがやっていることすべてを許容できるわけではない。先人たちが受けて来た殺戮の恐怖を、パレスチナ人に与えることにもなっているからだ。
本書の原著は2021年に刊行され高い評価を得たという。日本では2024年の今、まさに読まれるべき時期の刊行となったといえるだろう。

ライター・編集者。1980年埼玉県生まれ。月刊『WiLL』、月刊『Hanada』編集部を経てフリー。雑誌、ウェブでインタビュー記事などの取材・執筆のほか、書籍の編集・構成などを手掛ける。